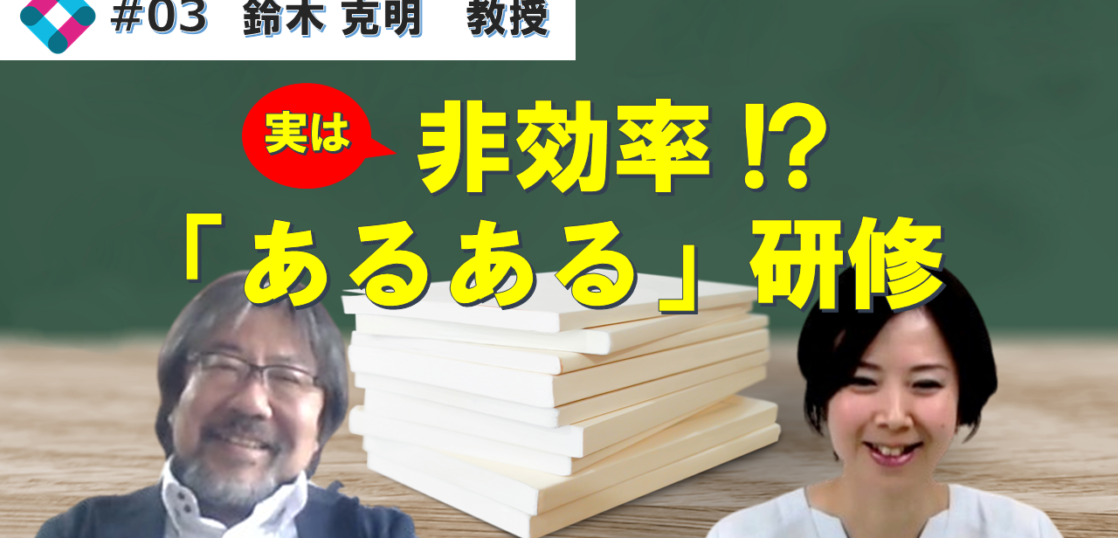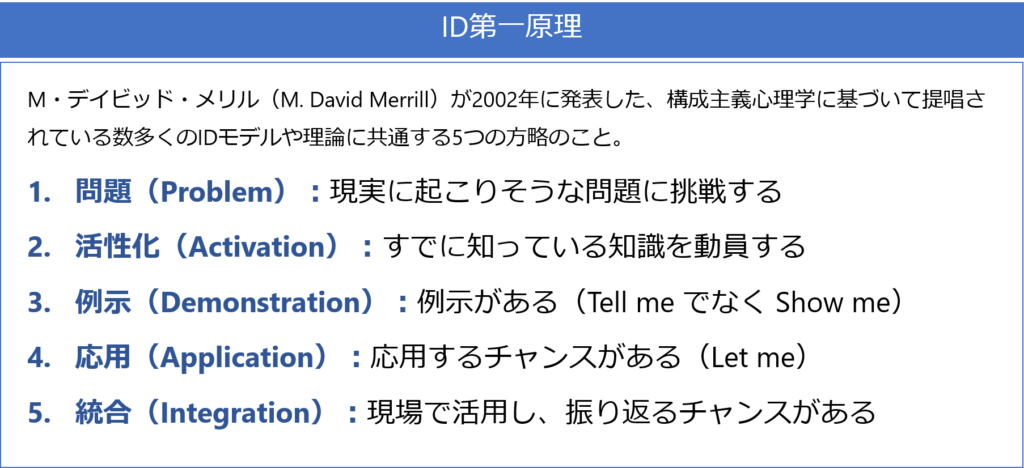研修の効果・効率・魅力の向上をめざして
~学習目標が明確なら、問題の半分は解決する~
学習目標は、研修や教材の作成においてもっとも根幹となる部分ですが、それゆえに「どう設定すればよいか分からない」「何から考えたらよいのか分からない」というお悩みをよく伺います。
そこで今回は、『企業の研修設計における学習目標の明確化』について、インストラクショナルデザインの第一人者である 熊本大学 大学院社会文化科学研究科 教授システム学専攻 鈴木 克明教授 にお話を伺いました。
企業研修における学習目標の明確化とその重要性について、全4回にわたってご紹介します。
Profile
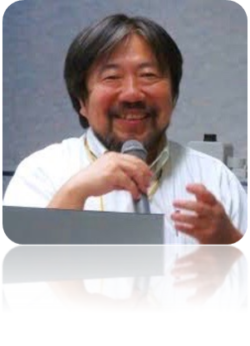
鈴木 克明(すずき かつあき)教授
熊本大学 教授システム学研究センター 教授 (センター長)
(兼任) 社会文化科学教育部 教授システム学専攻 教授・専攻長
1959年生まれ。Ph.D.(フロリダ州立大学教授システム学専攻)。ibstpi®フェロー・理事(2007-2015)、日本教育工学会理事・第8代会長(2017-2020)、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長(2012-2015)、日本医療教授システム学会理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。主著に「研修設計マニュアル」、「教材設計マニュアル」、「授業設計マニュアル(共編著)」、「教育工学を始めよう(共訳・解説)」、「インストラクショナルデザインの原理(共監訳)」、「学習意欲をデザインする(監訳)」、「インストラクショナルデザインとテクノ ロジ(共監訳)」がある。
「学習者に自分で気付かせる」研修は非効率!? 気付かせるための濃密な仕掛けづくりが効果的な研修のカギ
何というか……ある意味、自分で気が付く人間は、研修に来る必要がないとも言えるわけですよね。
どういうことかというと、学習課題に自分自身で気が付ける人は、研修を受けずとも日々の仕事の中でどんどん気付いて成長していくことができて、それがある意味、今までの日本の質の高い労働力を支えてきている大原則だといえるのですが、それでは時間がかかり過ぎます。現場に行って意識的に「自分で気付くこと」を心がければ誰しも自身の課題に気付けるなんて、そんなわけはないですよね。
だからこそ、研修の場で課題場面をつくって“あえて”失敗させて、課題をうまく克服できるようになるまで面倒を見てから現場に出す、という研修の枠組みが必要なのです。
学習者が、気付くべき課題に自分ひとりできちんと気が付けるほど現場は都合よくはありませんが、研修の場であれば、そういった課題場面を意図的につくることができるというメリットがあります。
では、「研修の意図を押し付けたくない」「学習者自身に気付いてほしい」という観点をどう捉えるべきかというと、明示はせずに意図としてとどめておく、という考え方も当然あるでしょう。「言わないで、やらせて、失敗させて、考えさせて、何がまずかったか自分で気付かせる」ということをポリシーにするのであれば、それはそれでよいと思います。ただし、研修の中で学習者が自身の課題に気が付けるようにするための場面をどのようにして濃密に仕込んでいくかは、研修を作る側がしっかりと設計していかなくてはいけないところです。
その失敗の場面をどう作るかですが、何も場面を徹底的に作り込んで「ほら、できないじゃないか。これができなきゃ駄目だ!」と教条主義的に押し付ける必要は一切なくて……例えば、チェックリストを用いて、現状何ができていて何ができていないかを自分でリフレクションしてもらい、気付かせるような方法などがあります。何が失敗したか分かるまで自分で考えさせるというやり方もありますが、チェックリストを活用できるような場面であればそれを用いて日常をリフレクションするところから研修を始めればいいと思います。
いずれにしても重要なのは、研修はアウトプットを中心にやらなくては駄目だということです。なぜなら、アウトプットさせることではじめて、できていない部分が明らかになるからです。アウトプットにより現状のできていない部分をまず確認し、それを克服してできるようになったかを、これもアウトプットで確認して、研修を修了するという形に持っていくべきです。
いろいろなやり方はありますが、リフレクション、アウトプット、失敗、失敗の克服、これらを軸に組み立てていくのがよいのではないでしょうか。
研修ではアウトプットを中心に据えて必要なインプットを実施する
なぜなら、例えば営業担当者なら、「商談ではこのようなメッセージを伝えましょう」「顧客のタイプに応じて攻め方を変えましょう」というように、会社が彼らに対してこうなってほしいというあるべき姿を押し付けているわけじゃないですか。
実際には押し付けているというよりも、会社としてそれが一番効果的であると判断したから、やってもらいたいと考えているわけですよね。よって、そういう会社として定めるべき方針を、自分で考えさせるとしたらおかしな話です。
押し付けということではなくて、基本的に、分かっていることは伝えたほうがよいです。なぜならそのほうが、効率が良いからです。そして、伝えただけでできるようになるかといえば、そんなことはないので、実際にやらせてみてできるかどうかをチェックする必要があります。
そのチェック方法は、先ほども言ったようにアウトプットです。たまたまできているのか、ちゃんと考えてできているのかを見分けるためには、なぜそうしたのかを聞いて理由を説明させないと分かりません。
インプット教育をすれば全員ができるようになるのであれば苦労はないのですが、残念ながらそうではありません。求めるアウトプットの方向性を示すために、チェックリストや必要な情報のインプットはしておきつつも、できるようにするためのアウトプットを繰り返しやっていくことが重要だといえます。
見本を示して、それをスッと真似できるようなら研修はいりません。わざわざ高い費用を払って人を集めて研修をしたり、そのチェックのための人員を配置したりせずとも、必要な情報をまとめた業務マニュアルなどの資料を渡せばそれで終わります。
そうならないように学習目標は精選して、会社にとって非常に重要な内容で、なおかつ伝えるだけでは分からないようなこと、できるようにならないことを取り上げる研修にすることがとても重要です。
逆に言えば、あまりに簡単なことを研修しても意味はないですよね。
そうして身に付けて欲しいこととのギャップを埋めていくためには、いろいろな仕掛けをして学習者にアウトプットの経験をさせなくてはいけません。ロールプレイをさせるなり、説明の仕方を文章で書かせるなり方法は何でもよいのですが、とにかく、アウトプットをさせるということが何より肝心です。